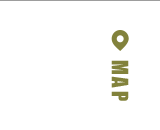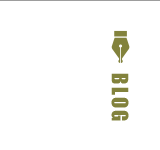日別アーカイブ: 2025年5月19日
ホームテックのよもやま話~第10回~
皆さんこんにちは!
株式会社ホームテック、更新担当の富山です。
【第2回】土木工事雑学講座 ~土木工事の種類とその役割を知ろう!~
本日は【第2回・土木工事雑学講座】をお届けします!
今回のテーマは、
**「土木工事の種類~主な工種とその用途」**です。
一口に“土木工事”といっても、その種類は実にさまざま。
道路をつくる工事もあれば、橋を架ける工事、川を整備する工事、さらには山の中にトンネルを掘るような工事まで、多岐にわたります。
私たちの暮らしの裏側で、どんな工種がどんな目的で行われているのか。
今日はその中から代表的な4つの工種をわかりやすくご紹介していきます!
◆ 道路工事 ~交通の命脈を整える~
まず最初にご紹介するのは、「道路工事」です。
私たちが毎日使う道路は、土木工事の中でも最も身近な存在のひとつです。道路工事では以下のような内容が行われます。
-
新設工事(道路そのものを新しく作る)
-
舗装工事(アスファルトやコンクリートで路面を仕上げる)
-
排水設備の設置(雨水の流れを調整)
-
歩道や縁石、ガードレールの設置
-
道路標識や信号の設置・調整
道路はただの「通る道」ではなく、人・車・自転車・物流のすべてをつなぐ“命の道”です。
老朽化した道路の補修や段差の解消など、地域の暮らしをより便利に・安全にするための細かな工事も日々行われています。
◆ 橋梁工事 ~人と地域をつなぐ架け橋~
次にご紹介するのは、「橋梁(きょうりょう)工事」です。
橋は、川や谷、道路・鉄道を越えて移動するための重要な構造物です。橋梁工事には次のような特徴があります。
-
橋の新設・増設
-
老朽化橋梁の補強・改修
-
定期的な点検と維持管理
-
鋼橋・PC橋(プレストレストコンクリート)・RC橋などの構造選定
地形や気象条件、交通量などを総合的に考慮し、場所ごとに最適な構造や材料が選ばれます。
特に最近では、長寿命化を意識したメンテナンス工事のニーズが高まっており、安全なインフラ維持に向けての取り組みが進んでいます。
◆ 河川工事 ~水害から街を守る最前線~
「河川工事」は、近年注目されることが多い分野です。というのも、地球温暖化の影響により、台風や集中豪雨による水害が全国的に増えているためです。
河川工事では以下のような内容が行われます。
-
護岸工事(川岸が崩れないよう補強)
-
堤防の設置・補強
-
浚渫(しゅんせつ)工事(川底の土砂を取り除いて流量を確保)
-
調整池や放水路の整備
-
生態系保全型工法の導入
また、ただ“コンクリートで固める”のではなく、**自然環境や生物多様性に配慮した工法(多自然型川づくり)**も積極的に取り入れられています。
命と自然を両方守る、まさに“防災”と“環境保護”の両立を目指す工事です。
◆ トンネル工事 ~山を貫き、街をつなぐ技術の粋~
最後にご紹介するのが、「トンネル工事」です。
山や都市部の地下を掘り進めて道路・鉄道・上下水道・電線等のルートを通すための工事で、特に技術力が問われる工種のひとつです。
-
山岳トンネル工法(NATMなど)
-
都市トンネルのシールド工法
-
地質調査と安全対策
-
換気・避難・排水といった付帯設備の整備
都市部では地上に土地がないため、地下空間の活用が進んでいます。地下鉄や地下道路、地下ショッピングモールなど、私たちの暮らしを下支えする空間が増えています。
こうした工事には、高度な掘削技術・構造計算・耐震設計が求められ、安全に長期間使用できる構造が作られています。
◆ まとめ:土木工事は“暮らしの骨格”をつくる仕事
いかがでしたか?
今回ご紹介した道路・橋・河川・トンネルの工事は、すべて私たちが安全・快適に暮らしていくために不可欠な存在です。
土木工事は、「つくる」ことだけが目的ではありません。
地域を守り、人をつなぎ、未来の生活を豊かにしていくための基盤を築いているのです。
以上、第2回土木工事雑学講座でした!
次回もお楽しみに!
![]()